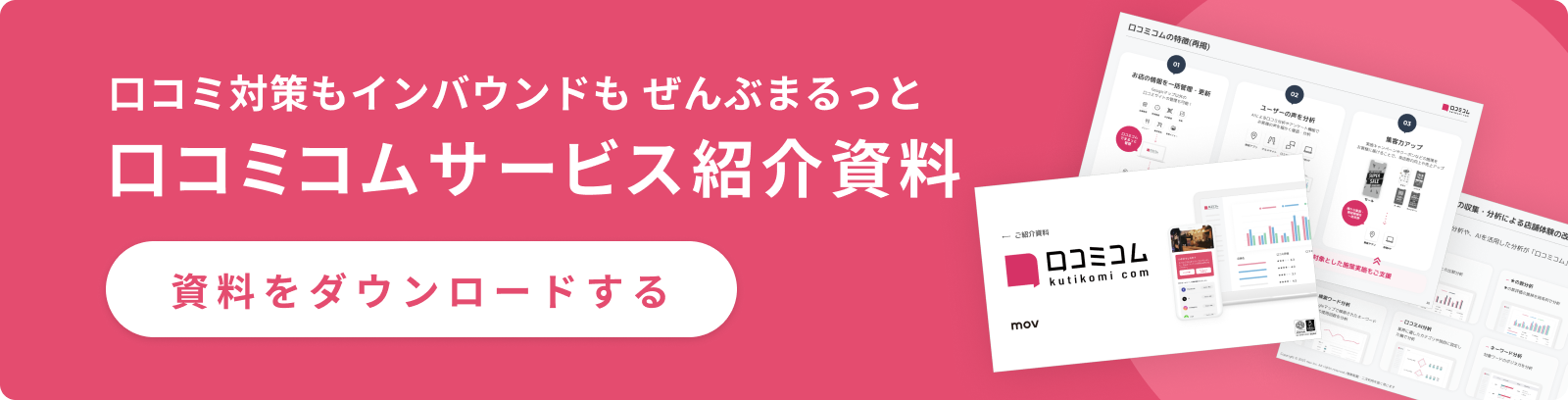多くのインバウンド客にとって、日本食は訪日する大きな目的の一つです。その高い需要に応えるため、飲食店のインバウンド対策は欠かせません。しかし「具体的に何から始めればいいかわからない」と悩んでいる飲食店も多いでしょう。
この記事では、飲食店が取り組むべきインバウンド対策を具体的に解説します。また、日本と海外の食文化の違いについてもご紹介します。「インバウンド対策を始めたいけど、何から手をつければいい?」と考えている飲食店の経営者や担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
インバウンド需要をつかむ!インバウンド対策を始めるなら「口コミコム」で→こちらをチェック
インバウンドの「今」を知る

飲食店が実施すべきインバウンド対策を紹介する前に、まずはインバウンドの現状について解説します。
インバウンド市場は自動車に次ぐ規模
コロナ禍以降、インバウンド需要は急拡大中で、2024年に日本を訪れた外国人の数は、過去最高だった2019年の3,188万人を大幅に更新し、3,687万人と過去最高を記録しました。
また、2024年のインバウンド消費額は、前年比で53.1%増、2019年比で68.8%増となる8兆1,257億円に達しました。これは国内の輸出産業で見ると、自動車に次ぐ2位の規模に匹敵します。
2030年には「6,000万人・15兆円」を目標にしていることから考えても、インバウンド市場が今後も成長し続けることが確実と言えます。
<参照>
- 日本政府観光局(JNTO):訪日外客統計
- 観光庁:訪日外国人の消費動向(2024年)
- 観光庁:観光立国推進基本計画(第4次)
8割以上が「日本食」を楽しみに訪日
観光庁の「訪日外国人の消費動向(2024年)」によると、インバウンド客が訪日前に期待することとして、「日本食を食べること」が82.2%と最も多いことが分かっています。
次いで多かったのは、「ショッピング」(62.8%)、「繁華街の街歩き」(54.7%)、「自然・景勝地観光」(53.6%)でした。
日本食を楽しみに訪日しているインバウンド客が多いことから考えても、今のうちからインバウンド対策を実施するのが望ましいでしょう。
「コミュニケーション」に困っている?
インバウンド客が訪日中に直面する問題の一つに、「店舗スタッフとのコミュニケーション」があります。
観光庁の「訪日外国人旅行者の受入環境に関する調査」によると、「ごみ箱の少なさ(21.9%)」に次いで、「施設スタッフとのコミュニケーション(15.2%)」が困りごととして多く挙げられています。前年度よりは減少したものの、依然として大きな課題です。
特に、コミュニケーションで困った場所として最も多かったのが「飲食店」でした。多言語対応を進めることで、競合店と差別化し、集客力を高める大きなチャンスでもあるのです。
インバウンド需要をつかむ!インバウンド対策を始めるなら「口コミコム」で→こちらをチェック
飲食店がインバウンド集客を成功するためのポイント

飲食店がインバウンド集客を成功させるには、やみくもに対策を行うのではなく、戦略的に進めることが重要です。
ここでは、特に意識すべき3つのポイントをご紹介します。
ターゲットを決める
まずは、ターゲットを決めましょう。インバウンド対策に限らず、集客においては「誰に」商品やサービスを届けたいのかを明確にする「ターゲット設定」が不可欠です。
ターゲットが不明確だと、最適な集客方法も、お客様の心に刺さるメニューやサービスも考えられません。
ニーズを把握する
次に、インバウンド客の視点に立って、店舗の魅力や彼らのニーズを洗い出しましょう。
日本人にとって魅力的なものが、必ずしもインバウンド客にとってそうとは限りません。逆に、日本人にとって当たり前のものが、インバウンド客にとっては新鮮で感動的な体験となることもあります。
何が響くか分からない場合は、SNSや動画サイトでインバウンド客が投稿したコンテンツを見てみるのがおすすめです。新たな魅力を見つけるヒントが隠されているかもしれません。
情報を適切に届ける
どれだけ魅力的なメニューを考えても、その情報がインバウンド客に届かなければ集客にはつながりません。多くのインバウンド客に伝わるよう、多言語で情報を発信し、魅力的な料理や店内の写真をたくさん掲載することが重要です。
もちろん、情報を発信するプラットフォームも重要です。国によって使用するSNSは異なり、たとえば中国ではX(旧Twitter)やFacebook、Instagramは使用できず、RED(小紅書)やWeiboなど独自のSNSで情報収集しています。
ターゲットに合ったプラットフォームで適切に情報を届けるようにしましょう。
| 国・地域 | 外国旅行の情報収集をする際に使うSNS |
|---|---|
| 中国 | TikTok(抖音)、Weibo(微博)、RED(小紅書) |
| 韓国 | NAVER、Instagram、Facebook、X(旧Twitter) |
| 台湾 | Facebook、Instagram |
| 香港 | Facebook、Instagram、Like Japan |
| アメリカ | Facebook、Instagram、X(旧Twitter) |
また、Googleマップは世界で20億人以上が使用していて、訪日中も飲食店の情報収集にGoogleマップを使用しています。
たとえばハラル対応のメニューを用意している飲食店であれば、Googleマップで「渋谷 ハラル」などと検索したときに検索結果に表示されるよう対策することが重要と言えます。
インバウンド需要をつかむ!インバウンド対策を始めるなら「口コミコム」で→こちらをチェック
【集客編】飲食店が実施すべきインバウンド対策3選

外国人観光客にあなたの飲食店を知ってもらい、足を運んでもらうには、効果的な集客施策が欠かせません。
ここでは、今日から始められる具体的な3つの集客方法をご紹介します。
- SNSで情報を発信
- Googleビジネスプロフィールで情報を整備
- 口コミ予約サイトで口コミを獲得
SNSで情報を発信
デジタルを活用した集客として特に有効なのは、SNSアカウントの運用です。SNSを活用すれば、見込み客に直接アプローチでき、より効果的なマーケティングにつながります。
繰り返しになりますが、ターゲットとする国の特性を理解して使い分けることが重要です。
Googleビジネスプロフィールで情報を整備
飲食店のインバウンド対策として欠かせないのが、Googleビジネスプロフィールを使った集客です。
SNSはターゲットによって対策すべきプラットフォームが異なるだけでなく、集客を成功させるためには時間とノウハウが必要です。一方、Googleビジネスプロフィールなら情報を整備するだけでインバウンド集客が期待できます。
インバウンド需要をつかむ!インバウンド対策を始めるなら「口コミコム」で→こちらをチェック
口コミ予約サイトで口コミを獲得
飲食店の集客においては、口コミ予約サイトの活用も非常に効果的です。多くのインバウンド客が口コミサイトを利用して飲食店を探すため、認知度向上や売上アップが期待できます。
代表的なサイトとしては、「中国版食べログ」とも呼ばれる「大衆点評」が挙げられます。
現在、訪日中国人の2人に1人が利用しており、「大衆点評」を活用した広告戦略で売上目標を達成した成功事例も存在します。
大衆点評を活用したインバウンド対策については、「大衆点評とは?店舗集客に不可欠な理由や使い方を徹底解説」の記事で詳しく解説しています。こちらもあわせてご覧ください。
関連記事:中国の地図アプリ「高徳地図」の使い方とは?店舗や施設の登録方法や集客方法を解説!
インバウンド需要をつかむ!インバウンド対策を始めるなら「口コミコム」で→こちらをチェック
【受け入れ環境整備】飲食店が実施すべきインバウンド対策6選

インバウンド客が快適に食事を楽しめる環境を整える、いわゆる「受け入れ環境整備」が重要です。
ここでは、顧客満足度を高めるための6つの対策をご紹介します。
- 無料Wi-Fiの設置
- メニューの多言語化
- モバイルオーダーシステムの導入
- キャッシュレス決済への対応
- ハラル・ベジタリアン・ヴィーガン対応
- スタッフ向け外国人対応研修の実施
無料Wi-Fiの設置
無料Wi-Fiの提供は、インバウンド客にとって重要なサービスの一つです。
観光庁の調査では、以前に比べてWi-Fiに関する課題は減少傾向にありますが、地域や店舗によっては、依然としてニーズが高いのが現状です。
Wi-Fi環境が整っていることで安心感につながるだけでなく、食事や休憩中にインターネットを利用でき、滞在中の満足度が高まります。
メニューの多言語化
来店してくれた外国人観光客に食事を最大限楽しんでもらうためにも、メニューの多言語化は優先して取り組むべき対策です。
英語は必須とし、できれば中国語(簡体字・繁体字)や韓国語など、複数の言語に対応できるとさらに良いでしょう。
すぐに多言語メニューを用意するのが難しい場合でも、まずは写真付きのメニューにすることで、言葉が通じなくても料理の内容を伝えることができます。
メニュー表を作り直すのが大変な場合は、店内の壁に料理の写真を貼り付けるだけでも効果があります。視覚的にメニューを伝えられるため、宗教上の理由などで食事に制限がある方にも、安心して注文してもらえるでしょう。
モバイルオーダーシステムの導入
言語の壁が大きな障壁となるインバウンド客にとって、モバイルオーダーは非常に有効です。多言語に対応したモバイルオーダーシステムを導入すれば、スタッフとの直接的な会話なしに注文が完結します。
これにより、注文ミスや意思疎通のストレスがなくなり、安心して食事を楽しんでもらえます。
また、インバウンド客は、日本のメニューに不慣れなことが多く、注文に時間がかかりがちです。モバイルオーダーなら、スマホの画面でメニューの写真や説明をじっくり見ながら、自分のペースで選ぶことができます。
モバイルオーダーは、顧客満足度の向上だけでなく、店舗側の業務効率化にも貢献するなど、インバウンド対策として有効な手段の一つと言えるでしょう。
キャッシュレス決済への対応
多くの国でキャッシュレス決済が主流となっており、特に中国や韓国からの観光客は、自国で普及しているQRコード決済(AlipayやWeChat Payなど)を頻繁に利用します。
現金しか使えない場合、両替の手間や、慣れない日本の硬貨・紙幣での支払い、お釣りの計算など、多くのストレスが発生します。キャッシュレス決済に対応することで、スムーズに支払いができるようになります。
また、客単価アップにつながる点もメリットと言えます。支払いが現金のみの場合、手持ちがないために来店を諦めるなど、大きな機会損失につながる可能性があります。
一方、キャッシュレス決済を導入すれば、顧客はスムーズに支払いができるだけでなく、現金よりも高額な消費につながりやすいため、客単価の向上が期待できます。
実際に、MMD研究所とSquareの共同調査では、キャッシュレス決済導入後に「客単価が上がった」と回答した店舗が17.2%にのぼります。
中国人集客については、「中国人集客、まず何をすべき?インバウンド担当者が最初に押さえるべき基本と最新トレンド」の記事でも詳しく紹介しています。こちらもご確認ください。
<参照>
MMD研究所・Square株式会社:【第2弾】実店舗オーナーによる運営店舗のキャッシュレス決済利用動向調査
ハラル・ベジタリアン・ヴィーガン対応
多様な文化や信条を持つ外国人観光客が、安心して食事を楽しめる環境を整えることも重要です。特に、ムスリム(イスラム教徒)にはハラル対応、ベジタリアンやヴィーガンには専用メニューが求められます。
一般社団法人ハラル・ジャパン協会によると、世界には18.5億人ものイスラム教徒がおり、そのうち約10億人がアジアに暮らしています。
また、観光庁のガイドブックによると、ベジタリアン・ヴィーガン人口は世界で約5.3億人に達し、その約75%がアジアの人々です。
アジアからの訪日客が増える中、これらのニーズに対応できている飲食店はまだ少ないのが現状です。だからこそ、今から対策を講じることで、新たな顧客層を獲得し、集客アップが期待できます。
<参照>
- 観光庁:ベジタリアン・ヴィーガン/ムスリム旅行者おもてなしガイド
- 一般社団法人ハラル・ジャパン協会:イスラム教について
スタッフ向け外国人対応研修の実施
インバウンド客が増える中、言語や文化に対応した接客スキルも重要です。
基本的な英語フレーズを習得したり、多言語対応のマニュアルを用意したりするなど、スタッフの異文化理解を深める研修を行うのも有効です。
スムーズで丁寧な接客ができれば、コミュニケーションミスやトラブルを防げます。また、外国人対応に慣れたスタッフがいることは、店の信頼性を高め、リピーター獲得や良い口コミによる集客にもつながります。
ただし、完璧を求める必要はありません。インバウンド客とコミュニケーションする上で重要なのは、何に困っているかを理解し、丁寧に対応しようとする姿勢です。
簡単な挨拶や、身振り手振りでも気持ちは伝わります。完璧に言葉が通じなくても、相手を理解しようとする気持ちがあれば、十分なコミュニケーションが取れるでしょう。
もしコミュニケーションが難しい場合、音声入力式の翻訳機やアプリを使うのも方法の一つです。日本語を外国語に翻訳する一方向のものだけでなく、日本語と外国語を双方向に翻訳できるタイプもあり、インバウンド客とのスムーズなやり取りに役立ちます。
自治体や国の補助金が利用できる場合もあるので、一度確認してみるのがおすすめです。
インバウンド需要をつかむ!インバウンド対策を始めるなら「口コミコム」で→こちらをチェック
知っておきたい!日本食に対するインバウンド客の本音5選

多くのインバウンド客にとって、日本食は来日の大きな目的の一つです。しかし、私たち日本人が当たり前だと思っていることが、彼らにとっては意外な驚きや発見となることもあります。
ここでは、外国人観光客が日本食に関して密かに感じている、日本人にはあまり知られていない「本音」を5つご紹介します。
インバウンド客にとって日本食は少ない!?
外国の食事と比較して、日本の飲食店は料理の量が少ないと感じるインバウンド客が多いようです。アメリカでは日本の「大盛り」サイズが一般的だったり、中国では日本の1.5倍ほどの量が「ちょうどいい」とされています。
この認識のズレを解消するため、メニューに写真を掲載して量を視覚的に伝えたり、肉のグラム数を明記したりする工夫が効果的です。これにより、インバウンド客は安心して注文でき、満足度向上にも繋がります。
インバウンド客からラーメンが大人気
日本の国民食であるラーメンは、インバウンド客からも絶大な人気を誇ります。観光庁が実施した「訪日外国人の消費動向(2024年)」によると、「最も満足した飲食」で肉料理に次いでラーメンが2位に輝いています。
台湾・香港人向け訪日観光情報サイト「樂吃購(ラーチーゴー)!日本」を運営するジーリーメディアグループの調査によると、日本を訪れるほぼすべての台湾・香港人が、旅行中にラーメンを食べていることが分かりました。
ラーチーゴーの陳怡秀(チン・イーシュウ)編集長によると、「日本のラーメンは単なる食事ではなく、ブランドとして確立されている」と語り、各地のご当地ラーメンを食べ歩くことを楽しみにしている台湾・香港人が多いということです。
<参照>
- 観光庁:訪日外国人の消費動向(2024年)
- 株式会社ジーリーメディアグループ:訪日経験あるほぼ全ての人「日本旅行でラーメン食べた」 台湾人・香港人1738人に食事に関するアンケート
中国や台湾では常温の水が喜ばれる!?
中国や台湾では、「冷えは健康の大敵」という東洋医学の考えが深く根付いています。そのため、冷たい料理や飲み物よりも、温かいものが好まれる傾向があります。
特に、氷の入った冷たい水は好まれません。中国人や台湾人観光客には、夏でもお湯か常温の水を用意するのがおすすめです。
<参照>
- 日本政府観光局(JNTO):外国旅行の動向(中国)
- 日本政府観光局(JNTO):外国旅行の動向(台湾)
「お通し」があるのは日本だけ!?
日本人にとって「お通し」は当たり前の文化ですが、インバウンド客は「頼んでいないのに料理が出てきた」「勝手に会計に加えられた」と戸惑います。
これは、外国人にとって「注文したものだけが料金に含まれる」という考えが一般的だからです。事前に「これはサービス料としてお一人様〇〇円いただきます」といった説明を英語や多言語で記載しておくと、トラブルを未然に防げるでしょう。
「おまかせ」の概念はないので伝わらない
懐石料理店などでは、料理人が献立を決める「おまかせ」が一般的ですが、外国にはこの概念がありません。そのため、メニューを見ずに注文するシステムに戸惑ったり、「シェフが勝手に決める」ということに不安を抱くことがあります。
特にアレルギーや宗教上の理由で食べられないものがある場合、意思疎通がうまくいかないとトラブルになりやすいので注意が必要です。
事前にアレルギーの有無や宗教上の制約を確認することが、安心して食事を楽しんでもらうために重要と言えます。
インバウンド需要をつかむ!インバウンド対策を始めるなら「口コミコム」で→こちらをチェック
飲食店のインバウンド集客事例4選

最後に、インバウンド集客に成功した飲食店の事例を紹介します。
【居酒屋】中国からのインバウンドに注目、「大衆点評」の活用で売上目標を達成
詳しくはこちら
【おにぎり専門店】とにかく「楽」。MEO対策もインバウンド対策も「口コミコム」で
詳しくはこちら
【焼肉店】都市部も郊外もインバウンドも。口コミコムでMEO対策を推進
詳しくはこちら
【ラーメン店】口コミコムの活用で、インバウンド対策や人事採用面のヒントも見えてきた
詳しくはこちら
インバウンド対策をして集客・売上アップ
今後も拡大が期待されるインバウンド需要。多くのインバウンド客が日本食を楽しみに訪日している今、飲食店にとっては大きなビジネスチャンスであり、インバウンド対策をすることで多くの集客が期待できます。
おもてなしの心で多様なニーズに応え、日本の飲食店の魅力を世界に発信していきましょう。
インバウンド需要をつかむ!インバウンド対策を始めるなら「口コミコム」で→こちらをチェック